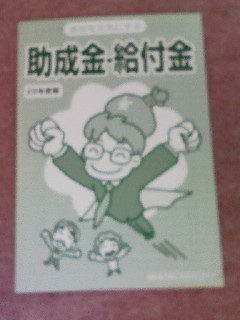
関西で事業を営む経営者の皆様へ。
当事務所では助成金に関する小冊子“会社を元気にする助成金・給付金”を無料で経営者の皆様にお配りしております。
国から支給される助成金にはどのようなものがあり、どのような条件をクリアすれば、もらえることができるのか?
そういった情報がこの1冊の網羅されております。
お申し込みはこちらの資料請求ページから
〒558-0045 大阪市住吉区住吉2-5-28
営業時間 | 9:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土日祝祭日 |
|---|
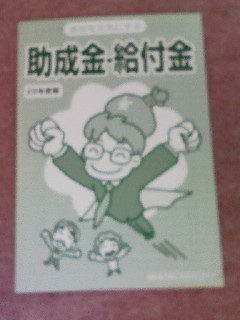
関西で事業を営む経営者の皆様へ。
当事務所では助成金に関する小冊子“会社を元気にする助成金・給付金”を無料で経営者の皆様にお配りしております。
国から支給される助成金にはどのようなものがあり、どのような条件をクリアすれば、もらえることができるのか?
そういった情報がこの1冊の網羅されております。
お申し込みはこちらの資料請求ページから
助成金とは、従業員を雇用している、事業主さんが国からもらえる、返済義務のないお金のことです。これは、事業主の皆さんが毎年納めている“労働保険料”が財源になっています。しかし誰でも彼でももらえるわけではなく、もちろん一定の支給基準があります。国が推し進めている雇用に対策に該当するような措置を講じた企業、事業所が支給の対象になってきます。
国が推し進めている雇用対策とはどのようなものなんでしょうか?例えば、昨今世間で聞くところの“少子高齢化対策” などはそのようないい例でしょう。60歳以上のいわゆる団塊世代が定年による引退を大量に控えているにもかかわらず、その引退世代を支えるべき、現役世代が圧倒的に不足してくるという状況が予測できるわけです。そのために現在国が講じている策としては、“子育てや育児と仕事が両立できるような環境作り” と“引退世代の新たな労働市場の形成”ということでしょう。育児を行う従業員のために働きやすいの措置を定めたり、“高齢者新たな雇用する”等の措置を講じた企業はこの助成金の対象にになってくる、ということです。
また、それに加え最近では、非正規雇用と正社員の条件格差の是正や、若年層のキャリアアップ対策も政府が取り組んでいるテーマになっています。
前述のように、返済義務がないので、うまく活用できれば、事業所をうまく切り盛りする潤滑油のような効果が期待できるのです。
まとめると…
・中小企業向けの採用関連(雇い入れ)、人材育成、女性や高齢者の活用、職場環境の整備に関するモノが多い
・財源は雇用保険料の事業主負担分
⇒だから活用しないと損!!
・労働保険(雇用保険・労災保険)の適用事業所であることが条件
・助成金は返済不要!!使い道は自由!!
⇒融資とは違います
・要件を満たせば支給される。
*経産省の補助金と違い採択(合格)制ではありません。
ということになります。
もちろん、当事務所でも助成金の取得のサポートに関しては、お力にならせて頂いております。
しかしながら、一般に助成金と言われるものも、色んな種類のものが存在します。その中には企業や事業所の方針のベクトルの向きと全く異なるような、支給要件を設けている助成金もあると思います。当事務所ではそのような企業や事業所の方針のベクトルの向きから全く離れるような、支給要件を設けているような助成金の取得は推奨いたしません。助成金の支給要件に該当するためだけに、会社の方針を変更したり、見直したりすることは、本末転倒であるといわざるをえないですから。
当事務所では、会社の方針のベクトルの向きに沿った支給要件に該当するような助成金、もしくは、会社の方針のベクトルの向きの先からは少しずれるけれども、ほんのちょっと手を伸ばせば届くような位置に存在するような助成金の取得サポートをさせていただいています。
しかしながら、前述した“少子高齢化対策”などは国が音頭を取って、勧めている国策ですから、将来的には、定年延長等の“高年齢者の雇用における活用”や“子育てと仕事が両立できるような就業体制”への変換を会社としては考えていかざるを得ないわけです。
法律上は、このような助成金の支給対象になるような措置を設けることを国は経営者に対して“努力義務規定”という形で課しています。条文上は“…するように努めなければならない。”という規定になっています。強制ではないですが、一定の義務を課しているわけです。
経験上、この“努力義務規定”は経過的措置であって、近い将来いずれ“義務規定”に変わり、強制力を伴うことが予測できます。“義務規定”に変われば、その措置を講じても助成金はもらえません。“努力義務規定”である間に、措置を講じれば、助成金が支給される可能性が高いわけです。であれば、今のうちに措置を講じて、助成金をもらっておくということも、一つの選択肢なのではないでしょうか?
以下に当事務所が取得を推奨している、助成金に関しては以下のものになります。 (支給要件等の詳細については、それぞれの助成金をクリックしていただくと、詳細の説明記事に飛ぶことができます。)
1.『採用』 に役立つ助成金
・お試し雇用をした場合に支給される助成金(トライアル雇用助成金)
・一定の就職困難者を雇用した際に支給される助成金
・高齢者の新たな雇い入れに関する助成金の詳細はこちらから
・非正規従業員の正社員化等に関する助成金(キャリアアップ助成金ー正社員化コース)
2.『子育てなどの両立支援』に関する助成金
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
3.『人材育成』に役立つ助成金
・新制度等を導入することにより、従業員のキャリア形成の補助をする助成金
人材開発支援助成金(制度導入助成)
・従業員の各種訓練、研修をサポートする助成金
・有期雇用の従業員等非正規社員のキャリアアップをサポートする助成金
4.『職場環境の改善』に役立つ助成金
5.『健康診断』に関する助成金
当事務所では助成金獲得までのプロセスをトータルにサポートさせていただいております。
ご相談、お問い合わせはこちらから(以下バナーをクリック下さい。)
助成金:申請から獲得までどのようなフロー(流れ)で行うのか?
助成金を申請して獲得したいが、どのような流れになっているのかが、やったことがないのでわからないという方もおられるかも知れません。
ここでは、獲得までおおまかなフローをキャリアアップ助成金(正社員化コース)を例にとってレクチャーします。
対象助成金:キャリアアップ助成金(正社員化コース)
①対象従業員を正社員転換する1ヶ月前に都道府県労働局にキャリアアップ計画書を策定し提出

②就業規則に正社員転換制度等、非正規雇用者を正社員化する規定を制定する(労基署に届出)

③雇用して6ヶ月以上の有期契約雇用者(期間の定めのある労働者)を正社員に転換

④正社員へ転換後6ヶ月経過した後に支給申請書を労働局に提出

⑤審査後決定通知書が届き助成金が支給される。
*キャリアアップ助成金を例に取りましたが、どの助成金も申請から支給までの間に就業規則を作成し、労基署へ提出しているかのどうかの確認を取ることが多いように思います。
*最近の傾向として、キャリアアップ系の助成金は①のように申請前に何らかの宿題、課題を求められるものが多くなっています。
当事務所ではキャリアアップ計画書などの事前の宿題も含め、助成金の獲得にお力添えをさせていただいています。
この記事は私が書きました
児島労務・法務事務所 代表 児島登志郎
社会保険労務士・行政書士
組織心理士・経営心理士(一般財団法人 日本経営心理士協会 認定)
元大阪労働局 総合労働相談員
元労働基準監督署 協定届・就業規則点検指導員
社会保険労務士として開業する傍ら、大阪府下の労働基準監督署にて総合労働相談員、就業規則・協定届点検指導員を計10年間勤める。 その間に受けた労使双方からの相談数は延べ15,000件以上、点検・指導した就業規則、労使協定届の延べ総数は10,000件以上に及ぶ。 圧倒的な数量の相談から培った経験・知識に基づいた労使紛争の予防策の構築や、社員のモチベーションを高める社内制度の構築を得意分野としている。
当ホームページは情報の掲載に関しては、万全を施すべく尽力しておりますが、サイト運営者の私見に基づく記述も含まれるため、全ての事案に対しての絶対の保証をしているわけではございません。また、法改正や制度変更の際は記事の更新が遅れることがあります。当ホームページ掲載の情報の取扱いに関しては、閲覧者の責任においてお扱いいただきますようにお願いいたします。当ホームページ掲載情報の扱いに際し、個人もしくは法人が何らかの損害を被ったとしても、児島労務・法務事務所ではその責任を負いかねます旨予めご了解下さい。
当サイト掲載コンテンツの全部または一部の無断複写・転載・転記を禁じます。
受付時間:9:00~18:00
定休日:土日祝祭日
大阪の社労士、就業規則の児島労務・法務事務所のホームページです。
就業規則の作成・変更を主力業務としている、大阪市住吉区の社会保険労務士です。元労働基準監督署相談員・指導員の代表社労士が長年の経験を活かし、御社にフィットする就業規則・賃金制度をご提供します。
サポートエリア)
最重要エリア)大阪市、堺市、吹田市等を含む大阪府下全域
重要エリア)京阪神地区、奈良地区
*オンライン(Zoom)でのお打合せにより就業規則作成、賃金制度構築等のサービスは全国対応可能です。大阪より遠方のお客様もお気軽にお尋ねください。
サービス内容のご質問、お見積もり依頼歓迎。
込み入った事案の労働相談は必ず事前予約下さい。(飛び込み対応は致しません)

大阪の社労士、行政書士の児島です。私は10期勤めた労基署の相談員時代に、通算件数15,000件以上もの労働相談を受けてきました。また、年間に300件以上の民間企業・法人の就業規則のチェックを行っており、これらの経験で培った、労働トラブルの予防に対する引き出しの数の圧倒的な多さが当事務所の武器です。