歩合給は営業担当者やタクシー運転手等、単に労働時間で仕事の成果が出るわけではなく、売り上げ等で評価されるべき仕事である場合にその導入が検討されるべきもの、あるいは導入されるものと考えます。
これにより、賃金が上がる人もいれば、当然下がる人も出てくるということになります。
そもそも、歩合給自体を導入すること自体が不利益変更になるのでしょうか?
裁判所の見解は“歩合給を導入したことにより、従業員の平均賃金がほぼ同一であったとしても、同じ売り上げ水準で成績を上げていたとしても、賃金低下の可能性がある以上は不利益変更にあたる”としました。
不利益変更に当たるとの判断が出た以上は次に合理性の判断をしていかなければなりません。
これも成果主義賃金の導入や定昇の廃止と同様の考え方で、
“導入にあたっての合理性は求めるが、高度の合理性までは求めない”
というのが一般的な考え方のようです。
と言いますのは、そもそも歩合給というのは、労働者の出来高に応じて賃金を配分するという考え方になりますので、業種(例えばタクシー運転手や営業担当者)などに関しては、労働生産性という観点から見ると、単に労働時間で成果を測る方法よりは公平で合理性があると考えられるわけです。
またそれ以上に従業員の勤労意欲を向上させる等の副次的な効果も考えられます。
よって、歩合給の導入の結果、賃金不利益が出る従業員に対する、経過的な救済措置や、労働組合や従業員との交渉をしっかり行う等、一定の手順を踏んで行うのであれば、変更自体は合理性があり、有効であるとの見解になる可能性が高いと考えます。
気をつけなければならないのは、例え合理性があり有効であったとしても、完全歩合の導入を検討する際には、労働基準法の27条(出来高払制の保障給)に抵触しない設計が必要となります。保障給をどのように、どれくらいのバランスで設計していくのかの検討は不可欠です。
歩合給を導入するにしても、一定の基本給は保障しなければならないということです。
後もう一つは、どの業界にも適合する賃金制度ではないということです。
この賃金制度を導入するときは、果たして歩合給という考え方が自分の業界にあっているのか?
ということを検証しなければならないでしょう。
上記裁判例で合理性があり有効と認められたのは、主にタクシー運転手の判例です。
ご覧の通り、賃金制度を見直す場合であたっても、労働契約法が施行後は、常に不利益変更の問題は避けて通れなくなっています。
不利益変更や訴訟のリスクを最小限に抑える!当事務所の『賃金制度改訂サービス』
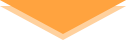
新たな規定の追加の場合はもちろんのこと、経営状況の悪化に伴う場合ですら就業規則の変更に伴う、労働条件の変更に関しては、やり方を間違うと、“合理性のない不利益変更”と判断されてしまう可能性があります。
当事務所では、様々なケースを想定して就業規則の変更のコンサルティングを行っております。
新たな制度の導入に伴う就業規則のご変更の際は、経験豊かな当事務所に是非、ご相談下さい。

