処遇改善等加算を有効活用!幼稚園、保育所の賃金制度、給与テーブル設計手法
幼稚園、認定こども園、保育所の賃金制度の設計の勘所について
平成30年度調査の厚生労働省の公式データ(賃金構造基本統計調査)によると幼稚園教諭、保育士の平均給与は全職種平均よりも3割程度下回っている事実が浮き彫りとなっています。
年収の全国平均
幼稚園教諭:360万円
保育士:356万円
(全職種の平均:560万円)
こういう事実が有資格者たちの『保育士離れ』の一因となっていると思われます。限られた人件費原資の範中で幼稚園教諭、保育スタッフたちのモチベーション維持をどのようにしてやり繰りするのかを考えていかなくてはなりません。
加えて今後の少子高齢化の影響で学卒者、有資格者が減少することが確実視されます。就活生たちに我が園を選んでもらうため、また既存の職員たちのリテンション策(引き留め策)としての賃金制度の設計を戦略的に考えていかないといけない段階にきているのではないでしょうか。
こちらでは、幼稚園、認定こども園、保育園の賃金制度、給与テーブルの設計の基本的な考え方を解説していきます。貴園の賃金制度構築の一助となれば幸いです
認可保育所の賃金設計の考え方
認可保育所の経営資源は国や地方自治体からの公的な運営支援金や拠出金にほぼ依存せざるをえない法人様がほとんどではないでしょうか。また人件費原資に目を向けても『処遇改善等加算』などの公的資金に強く依存せざるを得ない保育所が大半かと思います。
こういった事情を鑑みた場合、保育所、特に認可保育所のケースでは『使える賃金制度』として機能させるためには、行政から支給される『処遇改善等加算』の獲得を前提として、その支給の意図に沿った形でかつ、支給される人件費原資の額を見込んでの制度構築が求められます。
ではどのように処遇改善等加算と賃金制度をリンクさせていけばよいのでしょうか?以下の2つの考え方で見ていきます。
1)獲得原資を合理的な改善用途として運用できる賃金制度の構築
保育事業者を対象とした処遇改善等加算は大まかの分類すると加算Ⅰと加算Ⅱの2種類、これらをさらに細かく階層化すると、加算Ⅰが3層、加算Ⅱが2層と計5階層の成り立ちとなっています。
加算Ⅰの支給目的は施設(組織)の取り組みとしてスタッフ全体の給与の底上げということで、
①ベースアップを含んだ定期昇給原資(基礎分、公務員・民間格差是正分)
②組織全体の賃金水準の改善として(賃金改善要件分)
③組織としての職員のキャリア構築体系の整備(キャリアパス要件)
の計3層の構造となっています。
それに対して加算Ⅱの支給目的はリーダー職を含む中堅職のスタッフに限定して、賃金水準の引き上げを図り職場定着を安定されることを意図する支援金となり
④概ね3年以上の経験年数を持つ職務別分野リーダー対象
⑤概ね7年以上の経験年数を持つ副主任保育士、専門リーダー対象
の計2層の構造になっています。
よって、これら処遇改善等加算ⅠおよびⅡの計5つの階層ごとのそれぞれの支給目的、支給方法にリンクした形で、かつ見込まれる人件費原資に見合った形での賃金設計が望まれます
またこれら処遇改善等加算で支給された人件費原資には、スタッフの支給方法(還元方法)にも階層ごとに一定の制限がかかるために、そういった制限を踏まえたうえでの昇給ルールや各種手当や賞与等の設定が不可欠となります。以下に手当設定の考え方の一例をあげておきます。
例)処遇改善等加算Ⅱの原資を見越して役職手当を設定する場合
組織内での役職手当の支給対象者と処遇改善加算Ⅱの受給要件を合わせる必要がある。
よって単純に組織内での位置付けだけではなく、3年以上、7年以上の経験年数や各職務分野での研修の修了の有無等により役職手当の支給要件を検討しなければならない。
2)獲得要件に見合う賃金制度の構築
さらに言えば、処遇改善等加算(Ⅰ、Ⅱの双方)の獲得要件を満たすように賃金制度を整備する必要もあろうかと思います。
主な段階での加算の獲得条件を以下で見ていきます
・処遇改善加算Ⅰの3層目である“キャリアパス要件”を獲得するためには『職位、職責または職務内容に応じた賃金体系』の構築を求められます。それに加え『研修の機会の付与』や『能力評価の実施』等も行わなければなりません。
・処遇改善加算Ⅱの4層目(職務分野別リーダー)、5層目(副主任保育士、はそれぞれ、一定のキャリアや研修を積んだ中堅リーダー層の職員の人数に応じ支給額が決定されるので、支給の対象職員がその職位に該当するということが明確に区分けされている必要があります。
つまり、これらの獲得条件から読み取れる行政からのメッセージとしては、認可保育所では『職位や役割が明確に区分けされる資格等級制度を構築し、それぞれの職位にふさわしい処遇をすることが望ましい』と察することができます。
上記の解説を踏まえて、以下の表に行政から支援される処遇改善等加算に賃金制度をどのようにリンクさせていけばよいかということをまとめてみました。
| 加算ⅠorⅡ | 階層 | 内容 | 処遇改善の対象 | 賃金制度における課題・検討ポイント |
| 処遇改善加算Ⅰ | 第1層 | 基礎分・人勧(公務員と民間の格差是正)分 | 組織・施設の全体の処遇の底上げ | ・基本給の昇給ピッチ ・在職年数に沿ったモデル賃金カーブ |
| 第2層 | 賃金改善分 | ・基本給の昇給ピッチ ・モデル賃金カーブ ・賞与設計 | ||
| 第3層 | キャリアパス要件分 | ・資格等級制度 ・職位もしくは役割に応じた手当の設計 | ||
| 処遇改善加算Ⅱ | 第4層 | 職務分野別リーダー | 施設内の特定の職位の者のみが対象 | ・資格等級制度 ・職位に応じた手当の設計 |
| 第5層 | 副主任保育士・専門リーダー |
保育業、特に認可保育所については上記の表における『課題・検討ポイント』に沿った賃金制度を考えていくことが今後の行政からの支援金の“獲得”および“活用”のためには重要になってくるかと思われます。
*上記で取り上げた処遇改善等加算は当コラム執筆時点(令和2年6月)での全国共通の保育業向け支援金制度の概念に基づき解説記事を記載しております。各地方自治体で独自で支援金の支給基準を設けているケースもございますのでそちらにつきましては都度ご確認ください。
当事務所では、いく通りかの賃金制度設計のコンサルティング手法を持っており、都度経営者様からのご要望やご予算に合わせたやり方をご提案させていただいております。ここでご紹介する、給与設計ソフトを使った賃金設計はキャリアや職務と給与をうまく連動させるという意味においては認可保育所の賃金設計には非常に相性がよいかと思います。ぜひ一度ご覧ください。
(*姉妹サイト『大阪人事コンサルティングセンター』にジャンプします。)
幼稚園・認定こども園、認可外保育所の賃金設計について
処遇改善等加算として公的機関からの支援金支給の対象となるのは、上記で説明させていただいた認可保育所だけではなく、幼稚園、認定こども園、(認可外保育所のうち)企業主導型保育施設も支給の対象となります。よって、保育所や認定こども園、企業主導型保育施設の中でも、人件費予算を公的な給付に依存するようなケースであれば、上記で解説させていただいた『認可保育所の賃金設計の考え方』を踏襲いただければいいと思います。
同一法人で認可保育施設、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園等の形態が異なる施設を運営しているケースもあろうかとおもいます。そのような場合は『処遇改善等加算』を活用した賃金制度の運用をより慎重に進める必要があります。というのは、施設形態により受給できる施設、できない施設が出てきたり、都道府県をまたがって施設運営するケースでは自治体独自の追加加算の対象になる施設も出てくるので、保育士や幼稚園教諭としてキャリアや能力が同程度の職員であっても勤める施設によっては処遇の格差が出てくるケースも考えられます。そういった環境下でどのように公正公平な処遇を行っていくかということも課題になってこようかと思われます。
幼稚園、認定こども園での賃金設計でもう一つ課題になってくる事案が、リテンション策(離職防止策、引き留め策)としての戦略的な設計です。このページの最初の解説記事(⇒幼稚園、保育所、認定こども園が抱える『いまそこにある労務労務問題』)でも述べた通り、保育業界、幼児教育業界は一般企業などに比べて職層階級が少なく、幼稚園教諭や保育教諭、保育士等がなかなか明確なキャリア構築を描きにくいというのが人材定着を阻害する一つの要因になってきていると思われます。
『我が園に長期勤続すれば、これだけ成長できて、こんな素敵な未来が待っている!!』というメッセージを若手スタッフや就活中の学生たちにアピールできるような賃金制度に仕上げていきたいものです。
加えて処遇改善等加算の獲得要件にもある通り、幼稚園教諭、保育教諭のキャリア形成の道しるべをしっかり示すという観点からの賃金制度に作り上げていく必要があろうかと思います。
幼稚園、認定こども園の賃金設計には、スタッフ一人一人の成長段階がしっかりと把握でき、仕事や役割と処遇がきちんとリンクするような『資格等級制度』を用いて処遇することも選択肢の一つとなってくるでしょう。
当事務所では『資格等級制度』を活用し、組織の中での個々の役割や成長度合いを処遇に反映させ、かつ法人・企業の業績に応じた弾力性のある給与制度も含む『人を育てる人事制度』の構築をお手伝いをさせていただいております。
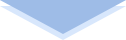
『人を育てる人事制度』のご紹介ページはこちらから
(*姉妹サイト“大阪人事コンサルティングセンター”にジャンプします。)
当事務所では、保育所、幼稚園、認定こども園の『スタッフのやる気を高める賃金制度』の構築も含め、採用支援、定着支援等、人事労務に関すること全般でお力添えさせていただくことが可能です。


