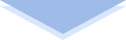昨今、中小規模の病院さんでは、他院との差別化を図る目的で、夜間の緊急の患者への対応サービスの充実をさせるため、コメディカル職の方、つまりレントゲン技師やPT,OTの方を夜間の時間帯に常時待機をさせておきたいというような相談をよく受けるようになってきました。
実際に待機中に急患が来られて、対応しなけければならないというケースは極まれではあるけれども、“この病院は夜間でも技師がいる”という安心感を地域の住民の皆さんに持っていただいて、他の病院との差別化を図りたいという意図なのでしょう。
この場合、労基法の原則から考えると、待機=事業主の指揮命令下にいる作業の手待ち時間という解釈になり、実際待機室でテレビを見ていようが、仮眠していようが急患が来れば対応しなければならない状況が続いている限り、労働時間としてカウントしなければならないということになってしまいます。
よって、この夜間の待機が通常の昼間の勤務を終了してから行われるのであれば、8時間超の法定外時間外労働の割増賃金と、夜10時から朝の5時までの間は深夜の時間帯の割増賃金が別途必要となってくるわけです。そういった勤務体制にすることによって、掛かってしまう人件費は馬鹿にならないでしょう。実働時間よりも待機時間の方が長いにも関わらず‥。
しかしながら、例外的に労働基準監督署長の許可を受けて、宿直勤務という扱いをすることができます。この宿直勤務という概念としては、ただ単に万が一のために待機しているだけ、拘束されているというだけで、労働の密度が非常に薄いようなケースに通常の労働時間、時間外労働、深夜労働の考え方とは一線を置いた考え方をしましょうということなのです。

よって、8時間勤務をした後に、宿直勤務を命じても、基本的には、通常の時間外労働や深夜労働の割増賃金の対象にしなくてもよく、宿直対象者の日額賃金の平均額の3分の1を下回らないような形で宿直手当を設定し、1回の宿直につきその宿直手当を支払えばそれでOKなわけです。
その際の注意点としては、通常のシフト勤務(昼勤)が終了した後に、休憩時間を設けた後に宿直勤務に入らなければなりません。この点は労働時間にカウントされる通常勤務と、労働時間のカウントから適用除外となる、宿直勤務のメリハリをつけようということなのだと思います。
また、基本的に常用雇用者でないとこの“宿直許可”の対象となりません。夜間の専門の待機要因の技師の従業員が別にいるのであれば、それは“宿直許可”の対象ではなく、“監視断続労働の許可”というまた、別の許認可申請の対象となってしまいます。
ただし、労基署の許可基準はあくまでも労働密度が低い場合に限定されるので、病院の職員さんの中でも、看護師さんや介護職員さん等の最前線で仕事をされている従業員さんに対しての許可申請は無理だと思います。
レントゲン技師さんやPTさんで“夜間の急患対応をする可能性があるけれども、そう滅多にあるわけではない。”といったようなケースで初めて許可の対象になる可能性が出てくるのではないかと思います。
当事務所が許可申請のご依頼を頂いた事案で、技師さんやPTの方であったとしても、救急指定病院等で急患の対応を頻繁にしなければならないようなケースでは、許可が下りなかったことも今までにありました。そのあたりの基準は私の経験則でも、お話できると思いますので、そういった夜間の待機体制の導入やそれに伴う許可申請をお考えの医療機関さんは一度ご相談下さればと思います。