そもそも、皆勤手当、精勤手当とは、従業員の出勤奨励を目的として、会社が決めた出勤成績を満たしている場合に支払われる手当です。
そもそも、労働契約自体が双務契約で、労働者は労働日には、労務を提供しなければならないという形になっているので、本来出勤日は有給取得を除いては、労働する義務が課せられているわけです。
よって、当然全出勤日に出勤しなければならないにも関わらず、出勤成績によって、精皆勤手当を支給することが、そもそもおかしいのではないかという考え方もあり、従来型の日本企業的なこの精皆勤手当をなくしてしまおうという、傾向が昨今強くなっております。
この精皆勤手当ですが、労働基準法では、支給条件や支給基準が明確に規定されている限りは、労働の対価として賃金に該当します。
よって、このような精皆勤手当を廃止または減額することは、不利益変更の問題が避けて通れないこととなり、やはり“高度の必要性に基づいた合理的な内容”であることが必要とされます。
この精皆勤手当の廃止、減額の合理性の考え方を判例等から紐解いていきたいと思います。
精皆勤手当を廃止するとしたとしても、その廃止が賃金制度の改定と関連して行われ、総支給額的にみれば、この手当が廃止されたとしても、結果的に賃金を減額していないケースであれば、廃止自体は賃金制度の改定により付いてくるもので、合理性を持つと考えることもできます。
ただし、賃金制度改定をするわけではなく、ただ単に、手当だけを廃止するというのであれば、これにより結果的に総支給額が減額されるのであれば、“高度の合理性”というところの抗弁が求められます。
会社が経営状態が芳しくなく、人件費削減の一環として、精皆勤手当を廃止する場合はどのような点に気をつけるべきでしょうか?
精皆勤手当というのは一般的に全体の給与額の中ではそれほど大きなウェイトを占めるわけではありません。
よって、会社経営上の人件費抑制が必要なケースでの廃止であれば、例えば、出勤成績を賞与査定に反映させ、出勤成績がよい従業員に対しては、賞与上で反映してあげる等の代替措置、経過的措置等を講じておくべきでしょう。
もちろん、その当たりを労働組合や従業員等と事前に協議をしたうえで、理解を得ておくことも、合理性を抗弁する上で不可欠なことはいうまでもありません。
ご覧の通り、手当の減額、廃止は当然のこと、複数の手当を一本化するにあたっても、労働契約法が施行後は、常に不利益変更の問題は避けて通れなくなっています。
新たな規定の追加の場合はもちろんのこと、経営状況の悪化に伴う場合ですら就業規則の変更に伴う、労働条件の変更に関しては、やり方を間違うと、“合理性のない不利益変更”と判断されてしまう可能性があります。
不利益変更や訴訟のリスクを最小限に抑え、経営合理化のための賃金制度の改訂をお手伝いします!!
当事務所の“賃金制度改訂サービス”はこちらから
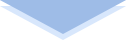
当事務所では、様々なケースを想定して就業規則の変更のコンサルティングを行っております。
各種手当の統廃合等で賃金規定をご変更の際は、経験豊かな当事務所に是非、ご相談下さい。

